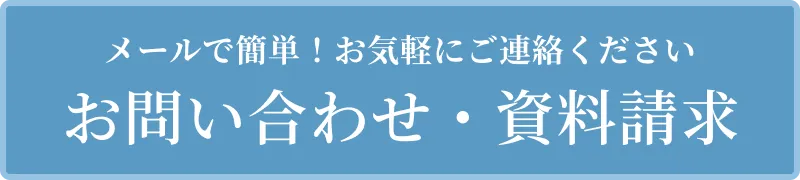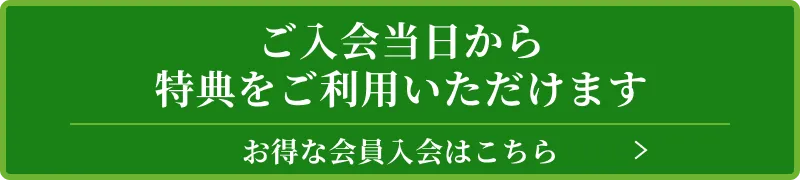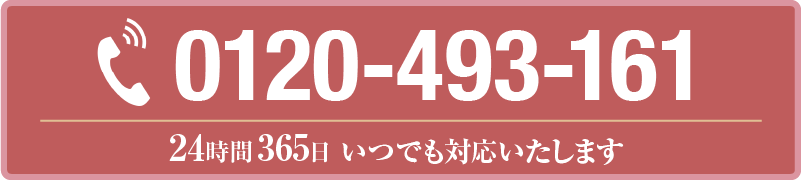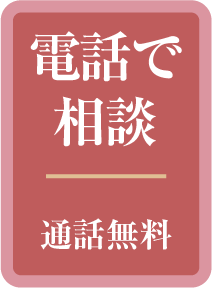白から黒へ。喪服の色が変わった理由

日本の喪服は、もともと「白」が基本でした。
白は「穢れを祓う」清浄の色。神道では死を穢れと捉え、白い衣で身を清める意味がありました。仏教でも白は「無垢」や「浄化」を象徴する色。死者が来世へ向かうための清らかな装いとして、白が選ばれていました。江戸時代の武家社会では、白の裃(かみしも)や白羽織が喪服として定着。女性は白無垢を着ることもありました。
明治時代になると、西洋文化の影響を受けて喪服の色が「黒」へと変化していきます。
西洋で喪服が黒なのは、単なる習慣ではなく「悲しみを静かに表す」「故人への敬意を示す」「場の格式を保つ」といった深い意味が込められています。宗教や王室文化、社会的マナーが融合して、黒が喪の色として定着したのです。
日本では明治11年、大久保利通の国葬で黒の大礼服が採用されたことが大きな転機となったそうです。
その後、新聞や雑誌で黒喪章が紹介されるようになり、庶民の間にも黒が「喪の色」として浸透していきます。昭和に入ると、洋装のブラックスーツが一般化し、現在の「黒=喪服」というイメージが定着しました。
喪服の色の変遷は、単なるファッションの変化ではなく、日本人の死生観や宗教観、そして時代の価値観を映し出す鏡のようなものです。
白から黒へ――その背景を知ることで、私たちは「弔う」という行為の意味を、もう一度深く考えるきっかけになるかもしれません。