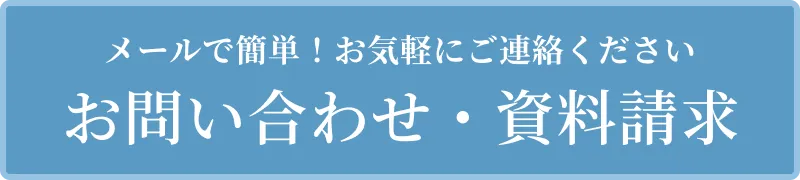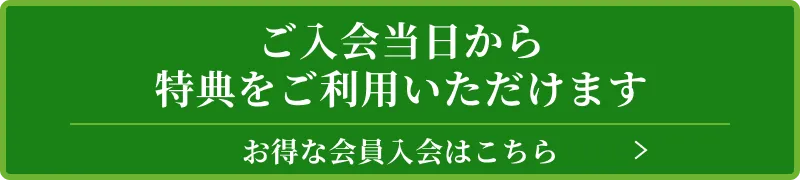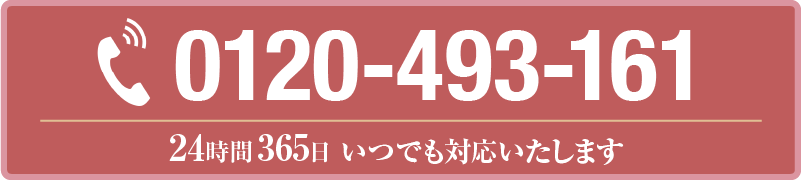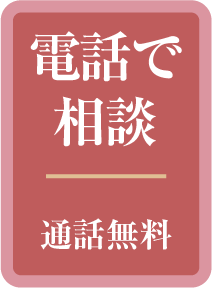🕯️ 仏具の燭台とは?灯りに込められた祈りの意味を知る

仏壇に欠かせない仏具のひとつに「燭台(しょくだい)」があります。燭台はロウソクを立てて火を灯すための道具で、「火立(ひたて)」とも呼ばれます。仏教において火は、暗闇を照らす智慧の象徴とされ、燭台に灯された火は仏様の教えを表す大切な存在です。
燭台は香炉・花立と並び「三具足(みつぐそく・さんぐそく)」と呼ばれる基本の仏具セットの一つ。仏壇に配置する際は、向かって右側に置くのが一般的です。火の光には「智慧」、熱には「慈悲」の意味が込められており、揺らめく炎が私たちの心を照らし、温めてくれると考えられています。
かつては油皿を用いて火を灯していましたが、明治時代以降はロウソクが主流となり、それに伴い燭台も普及しました。近年では安全性を考慮し、LEDタイプの燭台も登場しています。
燭台の形状や素材は宗派や地域によって異なり、鶴や亀を模した装飾が施されたものもあります。選ぶ際は宗派とともに仏壇のサイズや雰囲気に合わせることが大切です。また、火を消す際は息を吹きかけず、手であおいで消すのが礼儀とされています。
燭台は単なる照明器具ではなく、祈りと敬意を込めた仏具。その灯りに込められた意味を知ることで、日々の供養がより深いものになるでしょう。
佐賀県全域26ホール完備のJAセレモニーさがでは、皆さまに安心していただけるよう、葬儀の準備やマナーなどに関する豆知識を発信してまいります。事前に知っておくことで、いざというときに慌てずに対応できることもあります。これからもさまざまな情報をお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。ご不明な点がありましたら、いつでもJAセレモニーさがまでお気軽にご相談ください。
葬儀についてのご質問やお見積りのご依頼なども24時間365日受け付けております。家族葬・一日葬・火葬・一般葬、法事法要など地域の皆様に寄り添う葬儀をお手伝いします。