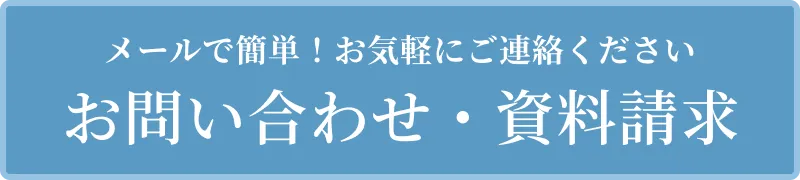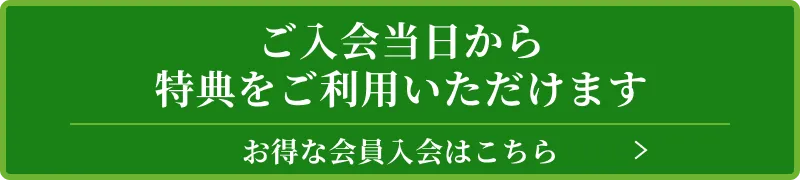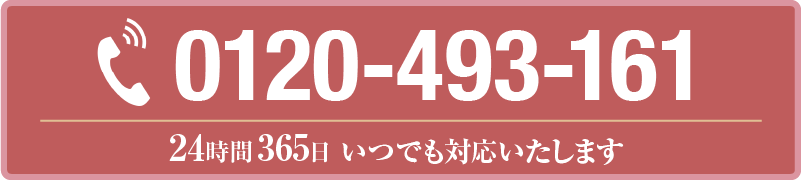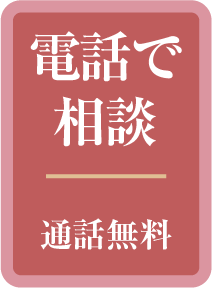「友引」に葬儀を避けるのはなぜ?

日本の暦には「六曜(ろくよう)」という吉凶を示す指標があります。その中でも「友引(ともびき)」は、葬儀の日取りとして避けられることで知られています。でも、なぜ「友引」では葬儀をしないのでしょうか?今回はその由来や現代の考え方について、ちょっとした豆知識をご紹介します。
○そもそも「友引」って何?
「友引」は六曜のひとつで、「友を引く」という意味に解釈されがちです。これが「亡くなった人が友を道連れにする」という迷信につながり、葬儀を避ける風習が生まれました。
しかし、実際の由来は「共引(ともびき)」で、「勝負なしの日」という意味だったとも言われています。つまり、もともとは縁起が悪い日ではなかったのです。
○地域によっては友引人形を使用
友引人形とは「友引」に葬儀を行う際、故人が“友を道連れにする”という迷信を避けるために棺に納める小さな人形です。
主に関西地方を中心に見られる風習で、「この人形を連れて行ってください」という意味を込めて用いられます。人形は葬儀社が用意することもあり、燃えやすい素材で作られています。
地域や家庭によっては使用しない場合もありますが、故人を思う気持ちと残された人々への配慮が込められた日本独自の習慣です。
○現代ではどう考える?
最近では「迷信にすぎない」として、友引でも葬儀を行う家庭も増えています。特に都市部では火葬場の稼働状況や参列者の都合を優先する傾向が強くなっています。
ただし、年配の方や地域によっては「友引は避けるべき」という考えが根強く残っているため、日程調整の際には配慮が必要です。
佐賀県全域26ホール完備のJAセレモニーさがでは、皆さまに安心していただけるよう、葬儀の準備やマナーなどに関する豆知識を発信してまいります。事前に知っておくことで、いざというときに慌てずに対応できることもあります。これからもさまざまな情報をお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。ご不明な点がありましたら、いつでもJAセレモニーさがまでお気軽にご相談ください。
葬儀についてのご質問やお見積りのご依頼なども24時間365日受け付けております。家族葬・一日葬・火葬・一般葬、法事法要など地域の皆様に寄り添う葬儀をお手伝いします。